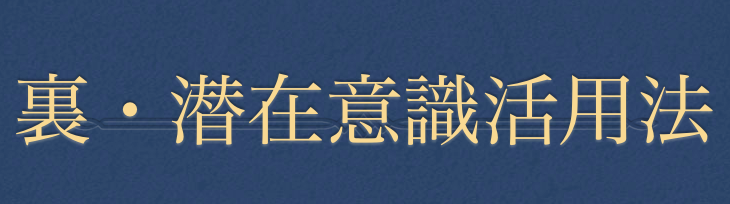人間関係苦手しか残らなかった
人間関係苦手の情報、案内
こんにちは。sachiです。
今日は息子の交流の授業中の過ごし方について
なんだかおもしろかったので書いておきます。
息子(ASD小2)はIQ平均以上、
ハイパーレクシア、感覚過敏、
不器用、人間関係苦手&回避的で、
典型的なアスペ孤立型です。
学力調査なども
平均よりかなりよい点がとれています。
が、息子の効率よい学習スタイルは
独学orマンツーマン。
多分、教員の指導書とか
市販の教科書ガイドとか1人で読ませておけば、
興味のある分野なら
先生が教えるより細かく詳しく覚えることが可能ではないかと思います。
勉強を理解する・・ということよりも
興味のなさすぎる分野があり、
必要な時にそれを記憶の中から取り出して
使いこなすことに不自由があるため
サポートが必要というか。
そのため、支援クラスでの学習指導は肌にあっても、
交流クラスでの一斉授業は
指示の要点が聞き取れなかったり、
それをする意図が分からなかったり、
書くのが苦手すぎてやる気がなかったりで
ついていくのが困難なようです。
学習参観に行っても
時間が過ぎていくのをひたすら待っている様子が
目に浮かぶような過ごしっぷり![]()
でも、いまはとにかく「交流クラスで過ごす」
ということを目標にがんばっています。
だから、交流クラスの先生も
ちゃんと座っていられるなら
「教科書ではない本を読んで過ごす」ことを
黙認してくださっています。
(席近くの床でゴロゴロして寝ちゃったり
ロッカーにはいりこんだりもしていますが![]() )
)
先生の怠慢?
息子のわがまま?
そんなことはまったく思いません。
むしろ限られた環境と条件の中で、
それを許してくださる先生をありがたく感じるし、
息子もよくがんばっていると思います。
(黙認してくれるクラスメートもまたすごい社会性・・・笑)
現在他県の教育委員会で指導○事をしている兄も、
過去に自分が中学校で担任したクラスに
アスペ孤立型の生徒がいたとき、
勉強も教えなくても既に分かっているし
宿題とかやることさえすれば
別の本を授業中に読んでいてもよいことにしていたと言っていました。
交流クラスでの過ごし方も、
段階的に踏んでいけたらそれでいいと思います。
***
さて、そんな息子と
昨日の登校中にこんな話になりました。
![]() 「学校では何して過ごしてるの?」
「学校では何して過ごしてるの?」
![]() 「本読んでる。授業のとき、ひまになるから
「本読んでる。授業のとき、ひまになるから
できるだけ長くて文字がいっぱいの本(図鑑など)を用意するの。
2ページを1時間かけてゆっくり読むんだよ」
![]() 「そう~。あ、ママが高校の時とかいたよ~
「そう~。あ、ママが高校の時とかいたよ~
先生にかくれてコッソリ本読んだり
別の勉強してる子~、いるいる、そういうことよくあるよ」
![]() 「そうなんだ?」←ちょっとうれしそう
「そうなんだ?」←ちょっとうれしそう
![]() 「うん、そうそう。
「うん、そうそう。
〇〇(息子)は自分のやり方で勉強していけばそれでいいんだよ」
息子の常人離れした知識欲や記憶力に
ある種の憧れすら感じることのある私は、
なんだかおもしろくてつい、肯定してしまいました((笑))
枠に無理にはめなくてもいいんじゃないかなって。
それに、本っていう逃げ場が息子にはあってよかったなって。
学校の授業で一般的にすすめられるとおりのことを
みんなと同じように順をおって
理解したりできるようになったりしなくても、
学習面では最終的に
『学習指導要領』の「ねらい」を押さえることができれば、
その方法や結果は多岐にわたってもいいと私は思います。
(『学習指導要領』とは・・・学校の教育課程の基準として定められているもの。
ほぼ10年に1度、改訂が行われます。
これにそって教科書がつくられたり、授業が構成されたりしています。
教員はもちろん目を通しますが、
市販されていて誰でも読むことができますよ。
教員必須の専門書ともいえますが、
特に難しい内容でもないので
興味のある方は読んでみてもいいかもしれませんね。↓↓)
|
217円
Amazon
|
ご縁があって、大学院時代に
学習指導要領の編集に関わっている先生や
教科書の編著者の一人である先生の指導を受けながら、
教育の研究をしていた時期がありますが、
多分、みんなが考えているよりも
学習スタイルはもっともっと柔軟になっていいんです。
(もちろん一斉授業のスタイルでは限界もありますが・汗)
がんじがらめに「こうじゃないといけない」と思っているのは
意外と末端の人たちであって、
核にあたるものや、
日本の代表として教育を考え
実際に動かしている人たちは、
実はそれほど厳しく規定をしていなかったり、
本当に必要なことを、その子の学びと成長のために、
無理なくすすめていくためにはどうしたらいいか
ということを考えていたりしています。
私が指導を受けた教科書の編著者の一人である先生は、
今思えば間違いなくADHDで、
小さいころはもちろん、教員
になってからも厄介者扱いされていたそうです。
自分の納得したことしかしないから、
上からの指導なんてまったくきかなかったとのこと(笑)
確かに私から見ても大変にアクの強い人ではありました。
研究を始めて学会にはいり認められ、
教科書の編著者になり、大学の先生になったら
みんなが手のひら返したように態度が変わって
ツッコミどころ多すぎてびっくりした、と言ってました。
そんな人がつくってたりするんですよ、教科書![]() 。
。
教科書通りにしなくったって、
「おもしろい!そういうのあっていい!
勉強ありきじゃなくて、子どもありきなんだから当然!」
って言ってくれそうです。
***
何だか言い訳がましくなってしまいましたが((笑))
交流での授業の過ごし方は、
ある程度は柔軟でいいんじゃないかなという考えの私と、
息子の授業中の実際の過ごし方について書いてみました。
まぁ、気楽にいきましょう。
人間関係苦手特集。
こんにちは。sachiです。
今日は息子の交流の授業中の過ごし方について
なんだかおもしろかったので書いておきます。
息子(ASD小2)はIQ平均以上、
ハイパーレクシア、感覚過敏、
不器用、人間関係苦手&回避的で、
典型的なアスペ孤立型です。
学力調査なども
平均よりかなりよい点がとれています。
が、息子の効率よい学習スタイルは
独学orマンツーマン。
多分、教員の指導書とか
市販の教科書ガイドとか1人で読ませておけば、
興味のある分野なら
先生が教えるより細かく詳しく覚えることが可能ではないかと思います。
勉強を理解する・・ということよりも
興味のなさすぎる分野があり、
必要な時にそれを記憶の中から取り出して
使いこなすことに不自由があるため
サポートが必要というか。
そのため、支援クラスでの学習指導は肌にあっても、
交流クラスでの一斉授業は
指示の要点が聞き取れなかったり、
それをする意図が分からなかったり、
書くのが苦手すぎてやる気がなかったりで
ついていくのが困難なようです。
学習参観に行っても
時間が過ぎていくのをひたすら待っている様子が
目に浮かぶような過ごしっぷり![]()
でも、いまはとにかく「交流クラスで過ごす」
ということを目標にがんばっています。
だから、交流クラスの先生も
ちゃんと座っていられるなら
「教科書ではない本を読んで過ごす」ことを
黙認してくださっています。
(席近くの床でゴロゴロして寝ちゃったり
ロッカーにはいりこんだりもしていますが![]() )
)
先生の怠慢?
息子のわがまま?
そんなことはまったく思いません。
むしろ限られた環境と条件の中で、
それを許してくださる先生をありがたく感じるし、
息子もよくがんばっていると思います。
(黙認してくれるクラスメートもまたすごい社会性・・・笑)
現在他県の教育委員会で指導○事をしている兄も、
過去に自分が中学校で担任したクラスに
アスペ孤立型の生徒がいたとき、
勉強も教えなくても既に分かっているし
宿題とかやることさえすれば
別の本を授業中に読んでいてもよいことにしていたと言っていました。
交流クラスでの過ごし方も、
段階的に踏んでいけたらそれでいいと思います。
***
さて、そんな息子と
昨日の登校中にこんな話になりました。
![]() 「学校では何して過ごしてるの?」
「学校では何して過ごしてるの?」
![]() 「本読んでる。授業のとき、ひまになるから
「本読んでる。授業のとき、ひまになるから
できるだけ長くて文字がいっぱいの本(図鑑など)を用意するの。
2ページを1時間かけてゆっくり読むんだよ」
![]() 「そう~。あ、ママが高校の時とかいたよ~
「そう~。あ、ママが高校の時とかいたよ~
先生にかくれてコッソリ本読んだり
別の勉強してる子~、いるいる、そういうことよくあるよ」
![]() 「そうなんだ?」←ちょっとうれしそう
「そうなんだ?」←ちょっとうれしそう
![]() 「うん、そうそう。
「うん、そうそう。
〇〇(息子)は自分のやり方で勉強していけばそれでいいんだよ」
息子の常人離れした知識欲や記憶力に
ある種の憧れすら感じることのある私は、
なんだかおもしろくてつい、肯定してしまいました((笑))
枠に無理にはめなくてもいいんじゃないかなって。
それに、本っていう逃げ場が息子にはあってよかったなって。
学校の授業で一般的にすすめられるとおりのことを
みんなと同じように順をおって
理解したりできるようになったりしなくても、
学習面では最終的に
『学習指導要領』の「ねらい」を押さえることができれば、
その方法や結果は多岐にわたってもいいと私は思います。
(『学習指導要領』とは・・・学校の教育課程の基準として定められているもの。
ほぼ10年に1度、改訂が行われます。
これにそって教科書がつくられたり、授業が構成されたりしています。
教員はもちろん目を通しますが、
市販されていて誰でも読むことができますよ。
教員必須の専門書ともいえますが、
特に難しい内容でもないので
興味のある方は読んでみてもいいかもしれませんね。↓↓)
|
217円
Amazon
|
ご縁があって、大学院時代に
学習指導要領の編集に関わっている先生や
教科書の編著者の一人である先生の指導を受けながら、
教育の研究をしていた時期がありますが、
多分、みんなが考えているよりも
学習スタイルはもっともっと柔軟になっていいんです。
(もちろん一斉授業のスタイルでは限界もありますが・汗)
がんじがらめに「こうじゃないといけない」と思っているのは
意外と末端の人たちであって、
核にあたるものや、
日本の代表として教育を考え
実際に動かしている人たちは、
実はそれほど厳しく規定をしていなかったり、
本当に必要なことを、その子の学びと成長のために、
無理なくすすめていくためにはどうしたらいいか
ということを考えていたりしています。
私が指導を受けた教科書の編著者の一人である先生は、
今思えば間違いなくADHDで、
小さいころはもちろん、教員
になってからも厄介者扱いされていたそうです。
自分の納得したことしかしないから、
上からの指導なんてまったくきかなかったとのこと(笑)
確かに私から見ても大変にアクの強い人ではありました。
研究を始めて学会にはいり認められ、
教科書の編著者になり、大学の先生になったら
みんなが手のひら返したように態度が変わって
ツッコミどころ多すぎてびっくりした、と言ってました。
そんな人がつくってたりするんですよ、教科書![]() 。
。
教科書通りにしなくったって、
「おもしろい!そういうのあっていい!
勉強ありきじゃなくて、子どもありきなんだから当然!」
って言ってくれそうです。
***
何だか言い訳がましくなってしまいましたが((笑))
交流での授業の過ごし方は、
ある程度は柔軟でいいんじゃないかなという考えの私と、
息子の授業中の実際の過ごし方について書いてみました。
まぁ、気楽にいきましょう。