ワーキングプアが選ぶ超イカしたバケツ10選
もちもち・ふわふわ❤️❤️❤️
たかがバケツ
保健所の何か月、何歳検診の際に、自閉症の子達は田舎なので顔見知りになったりします。その際、「もう2歳、3歳になるのに、いまだにおしっこもウンチもおむつでしかしない。トイレ完全拒否で困っている。」という話を聞きます。今回は、これは解決できるよ?と親族一同が確信している、その理由を書いてみようと思います。
自閉症児やアスペルガー、自閉症スペクトラムなどの発達障害児を育てていると、赤ちゃんからよちよち歩きを卒業するころに出てくる悩みが絶対的に2つあると思います。
まず発語。言葉がでない。
次に、トイレ。トイレトレーニングが一向に進まない。
発語については、身体的特徴としての障害の一つかもしれないけれど、脳内での思考や理解力には問題がない親族ばかりだ、ということを先の記事で書きました。今回のトイレトレーニングも、定型一般の親御さんの誤解があると思って、書こうと思いました。
まず、お子さんには癇癪やこだわりに独特の特徴がないでしょうか?
ほとんどの発達障害の子供は、とても小さい頃、0歳~3歳は障害特性が全面に出る時期だと思います。この時期は、子供の思考回路や興味、癖、過敏性などを発見できる一番貴重な時期です。この頃に得たデータというか、子供の特徴から、その先問題なく生活していけるように「こだわりを崩して自然なやりかたに導くこと」や「自分でできる工夫や方法を見つける」ことができるので、これら2、3年の間というのは、とてもとても貴重な時期です。ヒントがたくさんちりばめられています。
トイレトレーニングは、まさにその集大成です。お子さんのこだわりの部分がわかれば、その日のうちに解決します。それがわからない場合は、子供があきらめて、おトイレに行けるようになるまで(希望がかなわない、と我慢してあきらめて普通のトイレで排泄するようになるのは、たいてい小学校1、2年ぐらい)待ち続けることになります。
うちの一族の、トイレトレーニングはだいたい2歳で完了します。トレーニングというより、「お試し期間」です。あれこれ、こどもの こだわり点を見つけて、参考にして、この子はこんな点でトイレではできないのだ、ということを理解していきます。具体的に、うちの家族はどんなことがハードルになっていたのか、リストアップしてみます。
― お尻を便器につけること(皮ふと便器の接触)が無理。→ 和式トイレでさせるとその日からOKに。
― トイレの壁がタイルで怖い。(視覚的不安、恐怖) → 壁一面に子どもが書きなぐった画用紙の絵を貼るとできるように。
― トイレの仕組みが怖い(穴が開いている形状、水がたまっていること、水で流すことなど)→ トイレのタンクを使用しない。用を足した後は、バケツで流す。(水がない便器で用を足し、本人がバケツで流すとできた)
― トイレの仕方、手順になじむ時間がいる(新しいことに抵抗があるので、見て暗記するまで不安でできない)→ 親がトイレ行くたびに一緒にトイレにつれていく。扉を開けたまま、口頭で「おしっこしてます」「トイレットペーパーをこれくらいの長さまで引き出して、ちぎります」「紙でおしりを綺麗にふいています」「紙を便器に捨てました」「便器を綺麗にするために、水を流します」と実況中継します。
こんな感じでしょうか。
うちは田舎の家なので、和式と洋式のトイレの2種類あります。家族では圧倒的に、和式派が多いです。理由は、上に書いたように、お尻に便器が接触するということが無理だという人と、椅子と同じ体制で、排せつができるわけないという理由(椅子に座る度にもよおすならわかるけど、食事、勉強では排泄しないのにトイレは座って排泄するということが、生理現象としてもかなりの違和感がある)です。私も子供の頃は、和式派でした。今はどちらでもOKです。子供は家でも外でも和式オンリーです。
トイレに連れて行った時の子供さんは、おそらくよちよち歩きだと思うんですが、どんな反応していましたか?
不安そうですか?
怖がっていますか?
不安で壊そうなら、何が原因でしょうか?音?色?形?電気の色?
飛び跳ねたり、逃げようとしたり、無視したり、ぐにゃぐにゃになって聞こうとしないこと、ないですか?
子供がトイレのどこを見ているのか、その視線だけでは原因がつかめないのが発達障害児です。
なので、それまでの生活で「こだわっていること」から推測していく必要があります。
例えば、色にこだわりのある子は、気に入った色以外は抵抗があることが多いので、好きなのが赤なのに、青や緑、黄色の壁だと怖くてトイレに入れません。まだ赤以外にな慣れていない、それだけが理由です。
例えば、家や部屋の電気がオレンジ色なのに、トイレだけ青っぽい蛍光灯?電球?を使っている場合もありますが、これも色合いが違和感と不安をかもしだして、入れない子もいます。
例えば、洋式トイレに座ると足に土台があるんですが、それが不安定で嫌とか、高さが自分に合っていないからここは大人しか使わないはずのトイレで、無理に子供にさせているんだ、という思い込みで嫌がる子もいました。この考え方は、アスペルガーの子ですが、とても独特だと思いました。大人も子供もユニバーサル、全く同じトイレでするということを証明するために、スーパーやデパート、親族の家のトイレなど1日ツアーをして「数をたくさん見せて納得させる」と、ああ、家も外もみんなこの大きさしかないんだ、と理解するようになったという面白いケースです。この子も2歳台です。2歳でこの考え方をしていました。
私は洋式の便座の「深さ」が怖くて、使えませんでした。和式は深さがなく、浅いですよね。子供の私にはあれぐらいがちょうど我慢できる深さでした。2歳ぐらいで、一人でしていたと思います。
あと、高機能自閉症の子や、アスペルガーの子は視覚過敏や感覚過敏の他にも、上記であげた点以外に�
�理論的に理解できないから怖くてできない」というのが、根本的な理由のようでした。自閉症で、いつも一緒にトイレにいくけど、怖がって扉をあけていても近づかず、くるくる回っていたり、飛んでいたり、反対側の壁にふにゃふにゃになってくっついていたりしています。これが、理論的にわからない場所に連れてこられた時の反応です(うちの一族の場合)。
なので、仕組みが完全に理解できるまで解説がいるんですよね。感覚的に無理な部分は、色々試して、せめて入口に立って見られるぐらいまで試して試して試しまくりますが、感覚的な抵抗の問題が解決されて、入口に立って待てるようになったら、次は解説や仕組みを見せることで、トイレというものを理解させる必要があります。
これをすっ飛ばして、いきなり「ここでおしっこするのよ」とか「うんちするのよ」と言っても、その出したものがどこに行くのか、なぜそう強いられるのかさっぱりわからない「先の見えない不安」があるから、トイレはマジックボックスというよりはブラックボックスで怖いんです。
きちんと、理論的に理解できれば、理解できた瞬間から突然自分でトイレを使い始めます。納得したら早いのが特性ですし。
こういう理由を定型のお母さんに伝えると、「まさか」と言われることがほとんどなのですが・・・私は赤ちゃんの寝ころんでいる頃からの記憶もありますし、他の親族も、赤ちゃんの頃から大人と同じようにいつも「考えていた」と言いますから、やっぱり理解できないことをしない、こだわりがあるから、そのこだわりが問題でできない、と考えたほうが妥当なんです。
私のトイレに対する感想は「深すぎる」という直観的な嫌さかげんだったので、その当時2歳前、1歳台だったことを思っても、理由がちゃんとあったのです。兄弟や他の親族も、わが子も長じて理由をちゃんと説明している所を見ると、発達障害児の頭の構造は、このようにいちいち理由があると考えておいた方が「解決につながる」と思います。
最後に、「あきらめ」のことを書いておきます。
いつまでもおむつに排泄するの。とか
小学校に入っても、トイレで失敗したり、おむつで登園、登校、とか
トイレがあるのに、床にそのままする、お風呂でする、とかのケースについて。
これは、子供がそういう場所やおむつでしたくないけど、あきらめているケースだろうと思います。自分の快適な排泄場所が見つからないから、仕方なく、そのまましているか、おむつでしているだけです。あきらめている場合は、「排泄しても気にしている様子がない」場合が多いです。または、おむつで排泄して不快感もあらわにしているのに、おむつで排泄を続けている場合は、もう、快適なトイレの場所などないんだ、と決めてかかっているので、そのまましてしまっているんですね。
早めに、色々試して快適な「その子だけの、障害特性にあったトイレ」を発見または工夫して作り上げてもらえれば、それを入口にして、他の一般のトイレでもできるようになってきます。慣れてくれば、抵抗がぐんとなくなってくるので、気にしなくなっていく確率も高いからです。
ぜひ、色々子供をかんさつして、何にこだわる子なのかを参考にして、トイレの構造や色、形なども変えたり解説したりして(聞いてないようで聞いてます)みてください。ある日突然、突破口が見えることと思います。
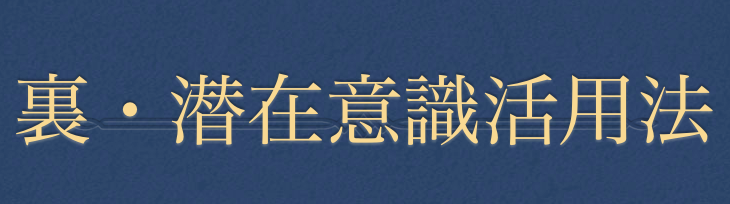



![洗車時、レジャー、掃除、防災時に!厚さ5cmに折りたためて場所を取らない◆薄く畳めるバケツ10リットル [コジット]バケツ ばけつ コンパクト 折りたたみ おしゃれ グリーン レジャー 災害 洗車 アウトドア 【RCP】](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cogit/cabinet/f1/03/090930.jpg?_ex=480x480)

